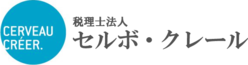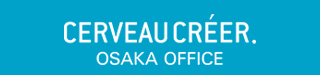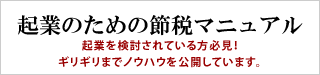配偶者に生前贈与された住居は遺産分割から除くとは?
2017/07/19
昨日、日経新聞の一面で大きく紙面をとって「遺産分割から住居除く、法制審試案、配偶者への贈与配慮」と題した記事が載っていました。
この記事でいうところの見直しはあくまで民法における「遺産分割」の改正に関する記事であって、財務省との折衝はこれからだと推測しますが、ひとまず現段階での審議内容について簡単にまとめておこうかと思います。
税金の取り扱いがどういう着地になるのかはおおよそ見当つきますからね。
法制審議会のHPを見に行ったのですが、このコラム執筆時にはまだ議事録がアップされていませんでしたが、詳細をご確認になりたい方はこちらで。
上記の要件は贈与税の配偶者控除(2000万円控除)を意識したものであることは明らかなので、婚姻期間の算定は入籍日から贈与時(相続発生時)まの期間で判定を行い、生前に贈与するということは贈与税の配偶者控除を適用した場合を意味するものと思われます(普通はないとは思いますが、配偶者控除を適用した場合の贈与に限定されていません)。
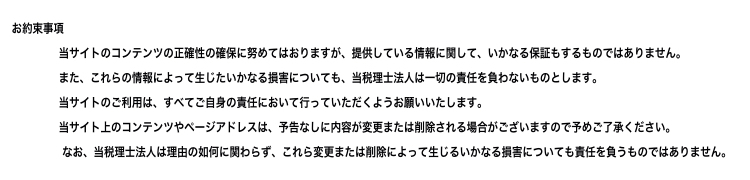
法務省:法制審議会ー民法(相続関係)部会 平成29年7月18日の法制審議会民法(相続関係)部会第23回会議がそれです。
日経の記事の内容を大まかにまとめると下記の2点です。
住居用の土地・建物の全部又は一部を配偶者に生前に贈与するか又は遺言書で贈与すると意思表示した場合には、当該住居については遺産分割の対象資産から除くというものただし、この適用を受けるためには、下記の要件を充足する必要があります。
- 夫婦の婚姻期間が20年以上であること
- 住居の全部又は一部を配偶者に生前に贈与するか、遺言書で住居を贈与する意思表示を行うこと(再掲)
また、遺言書で住居を配偶者に贈与するというのは、いわゆる「※死因贈与」に該当するものであると考えられます。
(相違点)
※死因贈与とは「私が死んだら○○に住居を贈与する」という贈与契約を贈与者(あげる人)と受贈者(もらう人)とが「申し込み」、「承諾する」ことにより成立する法律行為です。当然、死因贈与契約は贈与者が生前の間に実行しておく必要があります。似たような手続きに「遺贈」というものがありますが、これは亡くなられた人が遺言書で「○○に住居を相続させる」と書き残すことによって成立する法律行為です。日経新聞の記事だけでは、「死因贈与」と「遺贈」のいずれを指しているのかは読み取れませんが、いずれの場合であっても今回の改定の対象になるんじゃないかと思います。「死因贈与」と「遺贈」の論点をまとめておきます。
(共通点)
| 共通点 | 死因贈与 | 遺贈 |
| 契約の効力発生 | 贈与者の死亡時 | 被相続人の死亡時 |
| 税金の取り扱い | 相続財産に含めて相続税課税 | 相続財産に含めて相続税課税 |
| 相続税の小規模宅地の特例の適用の有無 | 適用あり | 適用あり |
現状の相続税(贈与税)のルールでは「死因贈与」又は「遺贈」による財産の移転は共に相続税の課税対象となりますので、税務上の取り扱いに大きな違いはありません。また、遺留分(相続人が最低限もらうことができる財産)の計算においても共にカウントすることになります。
(相違点)
| 相違点 | 死因贈与 | 遺贈 |
| 契約成立の要件 | 贈与者、受贈者双方の合意が必要。 | 被相続人の意思で足りる。 |
| 書面の存在の必要性 | 贈与契約 ※必ずしも契約書は必要ありません。 | 遺言書の作成 ※所定の書式での書面が必要です。 |
| 契約の撤回 | 受贈者の了承が必要となる。 | 新しい遺言書を作成すれば、新しい内容が有効になる。 |
日経新聞の記事だけではハッキリとはわかりませんが、記事の書き振りからすると上記のような住居の全部又は一部を配偶者に「生前に贈与」又は「死因贈与」ないしは「遺贈」している場合については、この遺留分の計算から除外するような民法の改正が盛り込まれているのではないかと考えられます。
ここからは妄想ではありますが、では上記のように民法が改正された場合にどうなるのかですが、基本的には税務上の取り扱いに変化はないと思われます。
「生前に贈与した残りの部分」、「死因贈与財産」、「遺贈財産」は共に相続財産として相続税の課税対象になると思われますし、これまでと同様に相続財産全体の評価額(課税価格)に応じた相続税の税率が適用されると思われます。
しかし、このような住居を遺産分割の対象に含めず、残りの財産だけを遺産分割したものの相続財産に占める住居の比重がとても大きい場合には、配偶者以外の相続人は相続した財産に見合わない相続税の税負担を負う可能性がでてきます。
配偶者の場合、「配偶者の税額軽減」という制度があり、配偶者が相続財産の1/2(1億6千万円を上限)までの財産を取得したのであれば、相続税がかからないようになっているのですが、この制度はあくまで配偶者の相続税からのみ控除してくれる制度であり、他の相続人の相続税に関しては効果がありません。あくまで相続財産全体の評価額(課税価格)に応じた税率により、各相続人が相続した相続財産に応じて相続税が課税されます。
つまり他の相続人にとっては、相続する財産はたかが知れてるにもかかわらず、相続税を支払ったらほとんど何も残らないというような状況もありうるということです。この部分については、これまでも弊害として顕在化していたものではありますが、何らかのバランスを取るような相続税の改正が行われるかもしれませんね。
遺産分割の協議中であったとしても預貯金を葬儀費用や生活費用に充てる仮払いを認める制度を創設する。
相続が発生した場合に、銀行に被相続人の死亡届を提出すると銀行口座が凍結されてしまいます。
こうなると、被相続人が旦那さんだった場合には残された家族が生活できなくなる懸念が多分にありました。
なので、これまで相続税のお仕事をさせていただいた方々も、ある程度まとまったお金を引き出してから、死亡手続きをしていることが多くあります。
また、通常は遺産分割がととのった段階で口座移管の手続きをすることになるのですが、最近は相続人の代表者口座に遺産分割前でも移管することができる金融機関も出てきましたが、それでも口座移管には2、3週間必要になります。
ただし日経新聞の記事だと仮払いの申請者が配偶者に限定されるのか、相続人になるのかはわかりませんね。
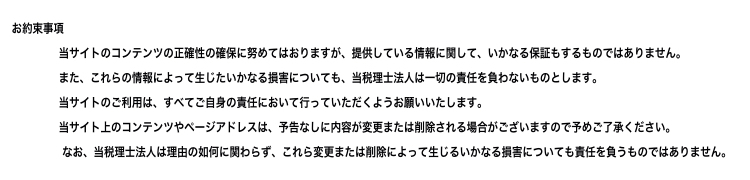
税理士法人セルボ・クレール
TOKYO OFFICE.
〒150-0013
東京都渋谷区恵比寿1-23-21 ヤマトハイツ802号室
TEL:03-6721-9737(営業時間:9:30〜18:30)
FAX:03-6721-9738
Mail:info(a)cerveau-creer.com
代表社員 税理士 長村 安展
公認会計士・税理士 渡邉 一生
OSAKA OFFICE.
〒530-0047
大阪市北区西天満1-1-11 レーベルビル4F
TEL:06-6809-1664(営業時間:9:30〜18:30)
FAX:06-6809-7664
Mail:info(a)cerveau-creer.com
代表社員 税理士 木下 陽介
公認会計士・税理士 辻秀明